みなさんは、「やり方や内容をよく理解していない仕事を任されてしまった」といった経験はありませんか?
新しい仕事や担当外の仕事を任されると、誰でも戸惑ってしまうものです。
しかし、ここでどのように対処するのかで、仕事のやりやすさが決まる重要な分かれ道なのです。
この記事では、やり方や内容がわからない仕事を任されてしまったときの対処法と、質問のしかたについてご紹介しています。
仕事がわからなくて行き詰っている人や、わからないけれど周囲の人に質問ができない人にとって有益な情報をまとめているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
仕事でわからないことが多いのはなんでだろう?まずは原因を知ろう
仕事でわからないことが多い状況には、いくつかの原因があります。
あなたがどの原因に当てはまるのかを理解することは、解決への第一歩です。
さっそくチェックしてみましょう。
新人や引継ぎをして間もないorその仕事をやったことがない
まだ仕事に慣れていなかったり、そもそもやったことがない作業では、わからないことが多いのは当然のことです。
新しいことをたくさん覚えなければいけないので、理解に時間がかかるとしても仕方のないことでしょう。
また、仕事を教える側に問題があることも。
時間がないなどの理由で上司や先輩による説明が足りないと、不明点は募るばかりです。
その上、周囲の人が忙しそうで質問しづらいといった問題が発生し、悪循環を引き起こす可能性も考えられます。
周囲の人に質問ができない

- 上司が怖くて話しかけづらい
- 忙しそうで、とても周囲に聞ける雰囲気ではない
- プライドが邪魔をして質問できない
- 評価が下がるのでは、能力不足と思われるのではと心配
- 質問に答える時間を相手にとらせるのが申し訳ない
などという理由で、仕事でわからないことがあっても周囲の人に質問できない人もいます。
特に、経験者やベテランになるとプライドが邪魔をして質問ができないと悩む人も多いです。
しかし、どのような理由でも仕事がわからない状況を無視することはおすすめしません。
ミスや重大なトラブルに繋がるおそれがあるからです。
質問することよりも、怖い思いや恥ずかしい思いをすることになりかねません。
何がわからないのか自分でもわからない
- 仕事を覚えたばかりである
- 仕事量が多い
- なんとなくわかったつもりでいた
といったことが原因で、「何がわからないのか自分でもわからない」という困った状況に陥ります。
どこから手を付ければ良いのか、誰に質問すれば良いのか、やり方や注意点などの詳細は?
疑問点は多いのにどこから質問するのが良いのか悩んでいると、仕事に集中するどころか、取り組むことすら難しいですよね。
しかし、そのまま放置しておくとより質問しづらくなってしまうでしょう。
質問をいつまでもしないとミスやトラブルが増え、会社に居づらい雰囲気になってしまい、仕事がおっくうに感じるようになることも考えられます。
仕事がわからないときの対処法
仕事がわからない状況は、自分がつらいだけでなく、ミスやトラブルによって周囲の人に迷惑をかけてしまう可能性があります。
それが続くと、信用を失い、会社に居づらくなってしまうことも。
それを防ぐためには、しっかりと対処することが必要です。
ここでご紹介する対処法は、基本的に上から順番に実行することで効率的に解決への道をたどります。
着実に行うために、1つずつ見ていきましょう。
わからないことをメモして整理する
社会人になるとメモをとることは必須です。
ここでのメモの目的は、わからないことを明確化して整理することです。
まずは仕事の流れをまとめてみましょう。
そうすることで、自分は何がわからないのかが理解できるはずです。
同時に、何のための作業なのかも考えてみましょう。
「こんな理由でこの作業をしている」ことを理解できると、仕事を断然スムーズに行えるようになります。
考えてもわからないことは、「質問することリスト」を作ってまとめましょう。
わからないことはまず自分で調べてみる
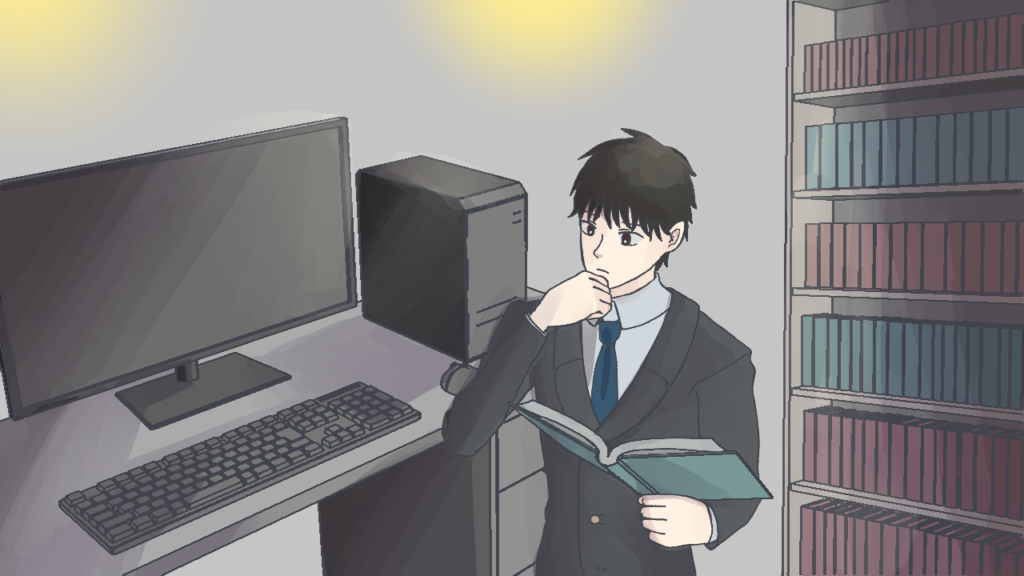
周囲の人に聞く前に、自分で解決できないか確認することが大切です。
何でもかんでも質問していると、周囲の人の時間を奪い、迷惑をかけてしまうことになります。
PC内や資料などで過去のデータを調べてみたり、マニュアルを読んでみたり。
以前教えてもらったことを忘れているだけかもしれないので、自分で書いたメモを見返すのも良いでしょう。
基本を見直すだけで解決できることもあります。よく確認してみてください。
それでもわからない場合は、次に進みましょう。
同僚や先輩に相談する
まず、わからないことを質問するのは悪いことではないことを心に留めておきましょう。
もちろん、相手に長々と時間をとらせてしまったり、同じ質問を何度も繰り返すことは例外です。
しかし、一人で考えるよりも質問をした方が早く仕事が進むことは事実です。
周囲の人としても、「早く仕事を覚えてもらった方が戦力になる」と考えている場合もあります。
潔く質問することもかしこい手段といえるでしょう。
むしろ、わからないことを放置しておく方がマイナス評価に繋がるリスクがあります。
ただし、質問する際にはいくつかの注意点が存在します。
相手に配慮した質問のしかたを身に付けよう!

ここでは、質問のしかたについてご説明しています。
みなさんは質問をする際に「相手に迷惑をかけてしまうだろうか」と考えてはいませんか?
確かに長々と話されたり、話がまとまっていないと迷惑に感じるかもしれません。
しかし、質問を受けることによって仕事を早く覚えるのであれば、快く答えてくれる人もいます。
それでも、質問をするということは相手の時間を使うことになるので、配慮を忘れてはいけません。
では、相手に配慮した質問のしかたを身に付けましょう。
時間帯に気を付ける
先ほども記載したように、質問をするということは相手の時間を使うという意味でもあります。
避けるべき時間帯は、
- 出勤時
- 退勤前
- 昼休み
などです。
忙しい時間であったり、プライベートな時間に質問することはやめましょう。
また、長々と質問しないように、「質問することリスト」を作成しましょう。
いくつかまとめて質問すると何度も話しかける必要がないので、相手の迷惑にもなりにくいです。
相手を思いやる一言を添えよう
- お忙しいところ失礼します
- お時間をいただきありがとうございました
など、相手を思いやる一言を添えましょう。
人間関係を穏便に築くには必要なことです。
「○○について質問があるのですが、5分だけお時間いただけますか?」とあらかじめ言っておくとより親切です。
「○○のことなら△△さんに聞く方が確実だよ」「5分だけならいいよ」などと相手に行動をゆだねることができるからです。
また、一から十まで質問することはやめましょう。
「質問することリスト」にまとめた、わからないことのみを確認するようにします。
「相手の時間を使っている」という意識は忘れずに持っておいてくださいね。
「○○しようと考えているのですが、先輩はどうですか?」と自分の意見を交えて質問するのも、仕事に前向きな姿勢が見られて好印象です。
間違っているや合っているなどは関係なく、周囲の人に聞く前に自分自身で調べていることが大切なのです。
質問内容は具体的に
長々と質問することはあまり良い印象を与えません。
何について、どこがわからないのかを明確に伝えるためにメモを活用しましょう。
質問に答えてもらっているときも要点はメモをしておきます。
あとで自分で見返して読みやすいようにまとめておくと、何度も質問することを避けられます。
ポイントは「理解できるまで聞くこと」です。
よくわかっていない、わかったつもりでいるまま質問を終えると、仕事がわからない状態から抜け出すことはできません。
せっかく質問をする機会を設けてもらったのですから、最大限仕事に生かしましょう。
仕事がわからないときはすぐに対処を!
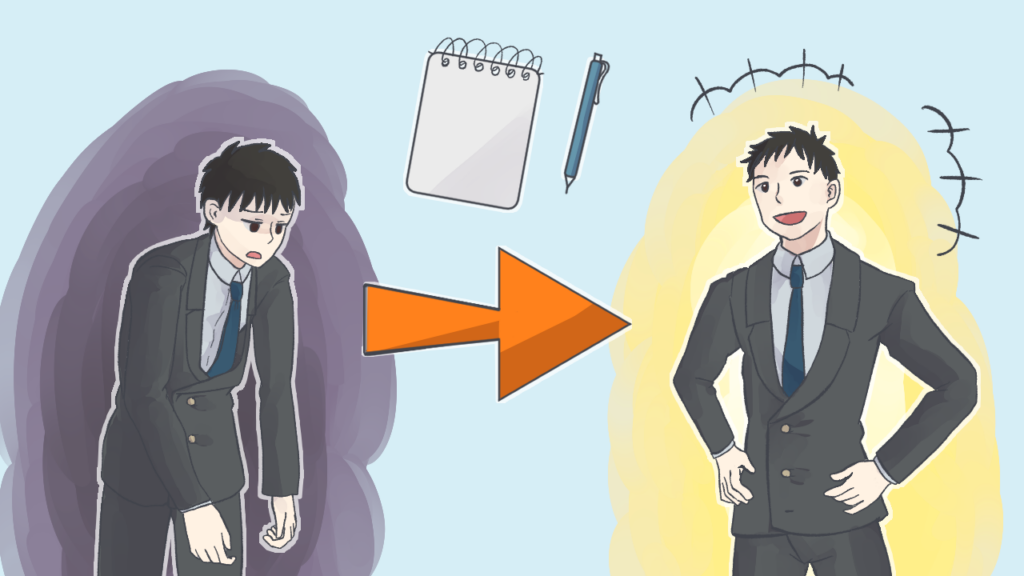
「仕事がわからなくて会社に行くのがしんどい…」といった思いをしないように、しっかり対処をしましょう。
わかったつもりやメモをするだけでは、この状況を変えることはできません。
メモをとる癖を身に付けるのはもちろん、自分なりにまとめておけばあとで見返すことができるので便利です。
また、疑問はその場で質問して解消しておくと、わからないことだらけになる状況を防ぐことができます。
仕事をしていく上で、疑問が発生することは当たり前のことです。
しかし、わからないこととどう向き合っていくのかが大切なのです。
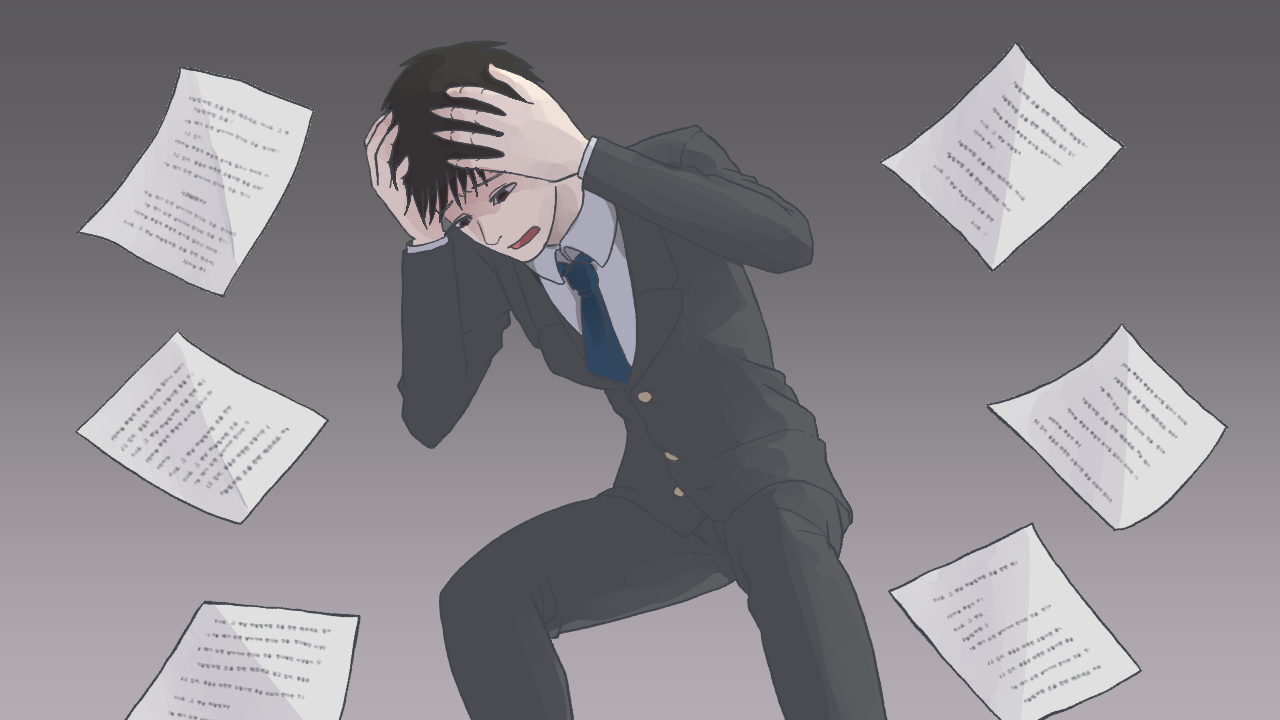


コメント