仕事で結果を残したり、スキルや経験を身に付けるためには目標設定をする必要があります。
なぜなら、目標は仕事をする上でさまざまなメリットをもたらすからです。
この記事では、目標の重要性や探し方、正しく設定するためのコツをご紹介しています。
目標設定には、「やるべきことを明確化させる」という目的があり、それがモチベーションや効率アップに繋がります。
結果的に、昇給や昇進のチャンスが巡ってくるかもしれません。
仕事でやる気が出なくて悩んでいる人や、より効率的に業務を進められるようになりたい人にとって役立つ情報をまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
目標設定はなぜ重要なのか?メリットは?
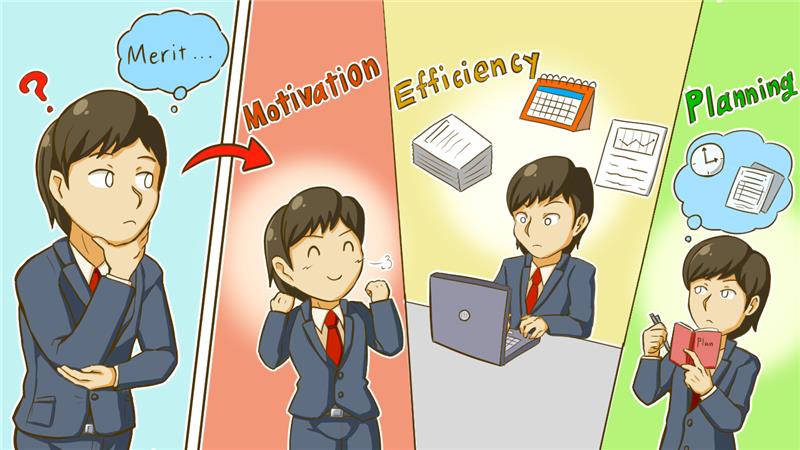
正直、目標を設定しなくても仕事をすることはできます。
しかし、目標を達成したときに感じられる喜びは、仕事をしていく上でとても大切なことです。
ここでは、目標の重要性についてお話しています。
設定する意味を知っておくことで、よりはっきりとした目標を立てられるようになるでしょう。
モチベーションアップが期待できる
仕事にクオリティを求めるなら、モチベーションは欠かせません。
しかし、毎日頑張って仕事をしていても、モチベーションの低い日もありますよね。
そこに、目標設定をしている人と設定していない人の差が生じるのです。
モチベーションを上げるには、「できた!」という達成感や、周囲の人から評価されることが効果的です。
上司や先輩に褒められると「もっと頑張ろう」という気持ちになりますよね。
こうした経験は、仕事でくじけそうになったときのバネにもなります。
目標を立てておくと、達成感を味わえますし、成長が早くなるので周囲の人から認められるようになります。
これにより、自信が持てるようになり、モチベーションがアップするのです。
仕事の効率化に繋がる
目標設定には、効率的に仕事を進められるようになるというメリットがあります。
「いつまでに、これだけの量を終わらせる」といった明確な目標があると、次に何をすべきかを考える習慣が身に付きます。
この習慣は、仕事での無駄な時間や行動を省く役割を担い、通常よりも早く作業を進められるようになります。
よって、目標設定は仕事の効率化に効果があるということです。
キャリアプランが描きやすい
目標設定に慣れてくると、長期的な目標(キャリアプラン)を立てられるようになります。
仕事を頑張っていると、昇給や昇進などに興味が湧いてくることもあるでしょう。
そこで、目標設定が役立ちます。
目標があると、「昇給・昇進をするにはどのような行動をするべきか」と筋道を立てることができます。
これにより、遠回りを防ぎながら目標へと向かっていくことができます。
つまり目標は、昇給や昇進までの道しるべとなるのです。
具体的な目標を設定をするためにテーマを決めよう!

一生懸命仕事に向かっていると、何から目指していけば良いのかわからない…と考えてしまう人も多いのではないでしょうか?
ここでは、目標設定をする際に役立つ「テーマ決め」についてお話しています。
どのような目標を設定するか迷っている人はご覧ください。
今の業務をより改善できないか考える
業務を進める上で重視することは、
- 正確さ
- スピード感
- 効率化
の3つです。
現在取り掛かっている仕事の中で、改善できそうな作業はありませんか?
資料作成1つとっても、「作る時間をより短縮して、効率化させたい」「みんなが見やすい資料を作りたい」など、たくさんの課題が浮かぶはずです。
改めて自分の仕事と向き合ってみましょう。
改善することができれば、作業が少し楽になることもあります。
自分の苦手なことから考える
誰しも苦手なことからできるだけ逃げたい、と考えてしまうものです。
しかし、苦手なことが少なくなると、どのような作業でも進んで行うことができます。
何よりストレスを感じにくくなるので、メンタルの面でもメリットがあるといえます。
目標設定をするときは、「いつまでにどのような方法で苦手を克服していくか」を考えます。
もし期限内に克服できなくても、やり方を変えてもう一度チャレンジしてみましょう。
苦手の克服にはどうしても時間がかかります。
しかし、克服するためにどうするべきかを考えて、策を講じることが大切なのです。
キャリアプランを立ててみる
仕事を続けていく中で、あなたはどうなりたいですか?
スキルを身に付けたい、昇進したいなど思い浮かぶことがあるでしょう。
それらを叶えるために、今自分がどのような行動をすべきなのかを考えてみてください。
例えば、スキルを身に付けたいなら
- 取得したい資格の試験が1年後にある
- 資格取得のために勉強をする必要がある
- 毎日1時間、勉強をしよう
といった具合に、連想ゲームのようにやるべきことを決めていきましょう。
そうすることで、筋道に沿った目標を設定することができます。
上司や先輩に相談してみる
上司や先輩は、あなたよりも経験豊富なはずです。
ですので、客観的な視点からアドバイスを求めることも有効な手段といえます。
自分では気が付かなかった課題や、足りていないスキルを指摘してもらえるチャンスです。
また、指摘をもらった課題を克服することができれば、職場での評価も高まるでしょう。
目標を設定するときはSMARTを意識しよう!

目標は、なんとなく設定するのでは意味がありません。
目標を設定するときは、SMARTの法則に準ずる必要があります。
SMARTとは、
- S(Specific):具体的である
- M(Measurable):測定可能、数字になっている
- A(Achievable):現実的に達成可能である
- R(Relevant):関連性がある
- T(Time-bound):明確な期限である
が合わさった言葉です。
1つずつ詳しく見てみましょう。
S(Specific):具体的である
目標はわかりやすくなければいけません。
例えば、「接客スキルをアップさせる」だけでは、達成のために何が必要なのかがいまいちピンときませんよね。
では、「3か月以内に接客スキルを向上させ、顧客満足度を10%アップさせる」ではどうでしょうか?
達成のために、話し方や自社製品のことをより学ぶなどの取り組みを考えることができます。
このように、目標は具体的でなければ次にやるべき行動が見いだせないのです。
M(Measurable):測定可能、数字になっている
これは、「目標に数字を使用しているか」ということです。
例えば、
- 2か月以内
- 来年の3月までに
- 10%アップ
といった具合に、目標に具体的な数字を取り入れましょう。
達成に近づいていく様子が目に見えてわかるので、モチベーションアップに繋がります。
ダイエットで「〇kgまで体重を落とす!」と目標を掲げるのと同じことです。
また、数字を使用することで、周囲の人が把握しやすいというメリットがあります。
例えば上司に共有すると、アドバイスやサポートが受けやすくなり、より早い成長が期待できます。
A(Achievable):現実的に達成可能である
「目標は高ければ高いほど良い!」と言われることがあります。
高い目標を掲げて実力以上の結果をたたき出す、ということでしょう。
しかし、仕事において高すぎる目標を設定することは逆効果です。
なぜなら、仕事にはモチベーションの維持がとても大切だからです。
「目標が達成できなかった」という失敗は、成功体験よりも強く頭に残ります。
それが挫折へと繋がり、モチベーション低下を招くのです。
頑張れば届きそうなレベルの目標なら達成感を味わいやすく、自信が持てます。
ですので、小さな目標をコツコツと達成するのがおすすめです。
R(Relevant):関連性がある
「この目標には、会社や部署ときちんと関連性があるのか」ということです。
組織に属している以上、周囲の人に認められることや貢献をすることが重要です。
ですので、目標を達成することで、会社や部署で成果を上げられるのかどうかを考慮しましょう。
表彰や褒賞金があるのなら、それらを意識するのも良いでしょう。
T(Time-bound):明確な期限である
目標を設定するときは、いつまでの達成を目指すのかも決めましょう。
期限がないとスピーディーさに欠けますし、達成感も半減してしまいます。
だらだらと仕事をしてしまい、モチベーションもいまいち上がりませんよね。
ですので、しっかりと明確な期限を決めて、目標達成のための行動に移りましょう。
仕事がデキる人になるには目標設定は必須!

小さな目標をコツコツと達成することで、モチベーションアップに繋がります。
また、達成するためにどのような行動をすべきかを考える能力が身に付くので、効率化も期待できるでしょう。
仕事をしていく中で、今よりも改善できることはたくさんあるはずです。
改善点を見つけ、克服していくことで、社会人としての成長が感じられます。
ぜひ、目標設定をして、仕事も充実感を得ましょう!



コメント